| かまくら子ども風土記(上巻)P126〜P128 | ||||
| 佐竹屋敷と大宝寺 | ||||
| 安養院を出てバス通りを逗子の方へ少し行くと、名越十字路で左へ折れて進むと又左へ入る小道の先に、佐竹屋敷といわれる所があります。日蓮宗の大宝寺のあるこのあたりの土地は、鎌倉時代に常陸の(茨城県)で勢力のあった佐竹秀義以来、佐竹氏代々の居住地といわれ、後ろの山を佐竹山といっています。山の形が扇の形に似て、中に三本のうねりがあり、左右を合わせて五本の骨のように見え、佐竹家の紋所はこれをかたちどって作ったものといわれています。 | ||||
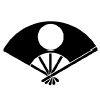 (図の白黒反転させものが佐竹家の紋) |
||||
| 室町時代の応永六年(1399年)佐竹義盛は出家して、家のそばに寺を建て多福寺と名づけました。その後、文安元年(1444年)一乗日出上人の勧めによって多福の名を山号とし、一乗院大宝寺と改めました。 大宝寺の本堂には、三宝緒尊・子育鬼子母神などがまつってあり、また新羅三郎義光と開山日出上人の像なども安置されています。 新羅三郎義光は、後三年の役のとき兄義家と力を合わせてこれをしずめ、甲斐守になり、佐竹屋敷のあたりにあった鎌倉の館に住むことになりました。義光は、後三年の役に大功をたてることができたのも、日ごろ信仰する守護神の多福稲荷大明神のおかげであると信じ、鎌倉の館のそばに多福神社を建てました。その後、多福稲荷を大町の八雲神社にあわせまつったことがありますが、明応八年(1499年)松葉ガ谷妙法寺の日証上人の考えで鎌倉の館(その後大宝寺)の場所に、再び大明神を移してまつるようになりました。当時は神仏と仏教の区別をしない時代でしたから、この多福稲荷大明神もその後、大宝寺の守り神として、また、開運勝利の神としてまつられておりました。 大宝寺の裏山の入口には、新羅三郎義光の霊をまつった石塔や、古い墓などがあります。 |
||||
 |
 |
|||
 |
||||
| 新羅三郎義光の石塔 | ||||
| かまくら子ども風土記(上巻)P128 | ||||
| 子育鬼子母神 | ||||
| 大宝寺の鬼子母神に次のようなことが言い伝えられています。 昔、一匹の鬼が千匹の子どもを持っていました。そして、毎日この子どもたちに人間の肉を食べさせていました。ある日、その中の一匹がいなくなってしまいました。母親の鬼は気が狂わんばかりにその子を捜しましたが、どうしてもわかりませんでした。だれか隠したのでしょうか。それは「お釈迦さま」だったのです。 母親はさっそくお釈迦様の所へ行きました。お釈迦様は母親に向かって、 「おまえは子どもに人間の肉ばかり食べさせているのではないか、人間だって食べられれば、その家族はみな嘆き悲しむのだ。これからは人間の肉の代わりにざくろの実が人間の味によく似ているから、それを食べさせるように。」 と言いました。 それから鬼は改心して子どもの守り神となりました。鬼子母神にざくろの実をお供えして、子どもがじょうぶでりっぱに育つようにと信仰する人たちが多いそうです。 |
||||
(C) Copyright Ricky Aoyagi 1998-2009. All Right Reserved.